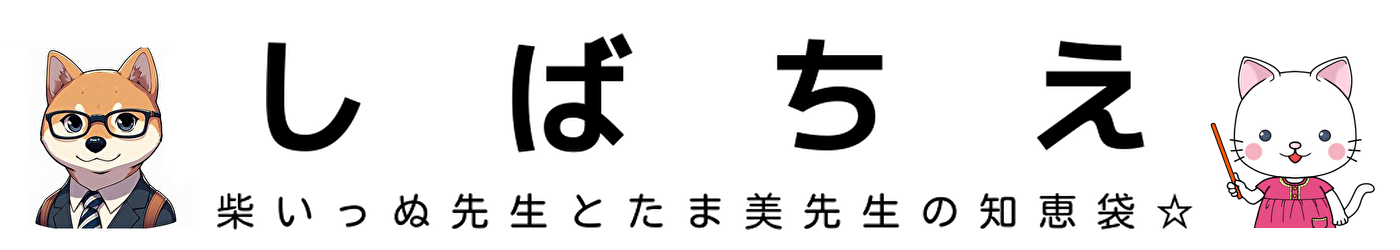「日の入り後、どれくらいで暗くなるの?」と疑問に思ったことはありませんか?
季節や地域によって、日没後の暗くなるスピードは大きく変わります。特に秋は「つるべ落とし」と言われるほど急激に暗くなりますが、夏は薄明が長く続くため、なかなか完全な夜になりません。
この記事では、日の入りから暗くなるまでの時間の目安、薄明(トワイライト)の仕組み、季節・地域ごとの違いを詳しく解説します。また、夜景撮影や星空観察に適したタイミングや、日の入り時刻を調べる便利な方法についても紹介します。
「なぜ日没後すぐに暗くならないのか?」「撮影や旅行に最適な時間帯は?」といった疑問にもしっかり答えていきます。

ぜひ最後まで読んで、夕暮れから夜へ移り変わる美しい時間をより楽しむための知識を身につけてください!
日の入りから暗くなるまでの時間はどれくらい?基本的な仕組み
日の入りと薄明(トワイライト)の関係

「日の入り」とは、太陽の上端が地平線の下に沈む瞬間を指します。
しかし、日の入りの瞬間に周囲が完全に暗くなるわけではありません。
むしろ、空にはまだ明るさが残っており、しばらくの間、薄暗い状態が続きます。
この時間帯を「薄明(トワイライト)」と呼びます。
薄明は、大気中の光の散乱によって発生します。太陽が地平線の下に沈んだ後も、その光が大気に反射し、空が明るく保たれるのです。これは、特に大気が多くの粒子を含むとき(例えば、湿度が高い日や大気汚染がある日)に顕著になります。
薄明には、大きく分けて以下の3つの段階があります:
- 市民薄明(シビルトワイライト):太陽が地平線の下6度までの位置にある時間帯。肉眼で物がはっきり見え、屋外活動が可能。
- 航海薄明(ノーチカルトワイライト):太陽が地平線の下6~12度にある時間帯。水平線がぼんやりと見え、海の上で航行が可能。
- 天文薄明(アストロノミカルトワイライト):太陽が地平線の下12~18度にある時間帯。肉眼ではほぼ暗闇に感じるが、完全な夜にはまだなっていない。
日の入り後、これらの段階を経て、ようやく空は完全に暗くなります。
日の入りから完全に暗くなるまでの時間の目安

日の入り後、完全に暗くなるまでの時間は季節や地域によって異なります。
一般的な目安として、次のようになります。
| 地域 | 日の入り後の暗くなる時間(平均) |
|---|---|
| 東京 | 約30~40分 |
| 北海道 | 約40~50分 |
| 沖縄 | 約25~35分 |
この時間差の理由は、緯度や地球の自転の影響によるものです。緯度が高いほど太陽が沈む角度が浅くなり、薄明が長く続きます。一方、赤道近くでは太陽がほぼ垂直に沈むため、暗くなるのが早くなります。
なぜ日没後すぐには暗くならないのか?
日没後すぐに暗くならないのは、大気の性質によるものです。地球の大気は、光を散乱する働きを持っています。特に、青い波長の光は散乱されやすく、これが夕焼けや薄明の色合いを作り出します。
また、大気の厚みや湿度、大気中の微粒子の量によっても、暗くなるまでの時間が変わります。たとえば、湿度の高い日は光が拡散しやすく、薄明が長く続く傾向があります。
さらに、都市部では光害(人工光による明るさ)が影響し、自然の薄明よりも長く空が明るく見えることがあります。逆に、山間部や海沿いでは、薄明が終わるとすぐに暗くなることが多いです。
薄明(トワイライト)の3つの段階とは?

市民薄明(シビルトワイライト)とは?どれくらい明るい?

市民薄明(シビルトワイライト)は、太陽が地平線の下6度までの位置にある時間帯を指します。
この時間帯では、まだ十分な明るさが残っており、街灯や車のヘッドライトなしでもある程度の視認性が確保されます。
一般的に、市民薄明の間は以下のような状況が続きます:
- 屋外で新聞や本を読むことができる
- 街灯や建物の灯りが点灯し始めるが、なくても歩行は可能
- 空の色はまだ青みがかっており、オレンジ色から徐々に紫がかった色へと変化
市民薄明は日常生活において最も影響を受けやすい時間帯です。例えば、ドライバーにとっては「対向車が見えづらくなる時間帯」でもあり、交通事故が増える時間帯とも言われています。特に、自転車や歩行者が視認しづらくなるため、注意が必要です。
航海薄明(ノーチカルトワイライト)とは?どんな影響がある?
航海薄明(ノーチカルトワイライト)は、太陽が地平線の下6度~12度に位置する時間帯を指します。この時間帯に入ると、肉眼での視認性が大きく低下し、街灯や人工照明がない場所ではかなり薄暗く感じられます。
航海薄明の間の特徴は以下の通りです:
- 水平線がぼんやりと見える程度の明るさ
- 星がはっきりと見え始めるが、まだ一部の明るい星のみ
- 夜景や天体観測には少し明るすぎる時間帯
この時間帯の名前は「航海」という言葉がついているように、昔の船乗りが海上で位置を確認する際の基準として使われていたことに由来します。

現代でも、星を使って航路を確認する「天測航法」を行う際に、この時間帯は重要な意味を持ちます。
天文薄明(アストロノミカルトワイライト)とは?完全な暗闇との違い

天文薄明(アストロノミカルトワイライト)は、太陽が地平線の下12度~18度に位置する時間帯を指します。
この時間帯に入ると、空はほぼ暗闇になり、肉眼で星がくっきりと見えるようになります。
天文薄明の間の特徴:
- 肉眼で天の川が見え始める
- 人工照明の影響が少ない場所では、ほぼ真っ暗に感じる
- 天文観測が本格的に可能になる時間帯
天文学者やアマチュア天体観測家にとっては、この時間帯が本格的な観測の開始時間になります。天体写真を撮影する際も、天文薄明が終わって完全な夜になった時間が最適です。
しかし、都市部では光害(ひかりがい)の影響が大きく、天文薄明が終わっても空が完全に暗くならないことがあります。特に大都市では、夜空がオレンジ色や青白く光って見えることがあり、これが星の観測を妨げる要因となります。
日の入りから暗くなるまでの時間は季節や地域で違う!その理由を解説

春・夏・秋・冬で暗くなる時間が違う理由
日の入り後に暗くなるまでの時間は、季節によって大きく異なります。これは、地球の傾きと太陽の沈み方が影響しているためです。

具体的には、次のような違いがあります。
| 季節 | 日の入り後の暗くなるまでの時間 | 特徴 |
|---|---|---|
| 春 | 約30~40分 | 徐々に日が長くなり、暗くなる時間も少しずつ遅くなる |
| 夏 | 約40~60分 | 日の入りの角度が浅いため、薄明が長く続く |
| 秋 | 約25~35分 | 「秋の日はつるべ落とし」の言葉通り、急激に暗くなる |
| 冬 | 約30~45分 | 日没の時間が早く、暗くなるのも早い |
特に夏と秋の違いは顕著で、夏は長時間薄明が続くのに対し、秋はすぐに暗くなります。これは、秋は太陽の沈む角度が急であり、大気中の光の散乱が少なくなるためです。
地域(北海道・東京・沖縄)ごとの日没後の暗くなる時間の違い

地域によっても、日の入り後に暗くなるまでの時間が異なります。これは緯度の違いが影響しています。
- 北海道(高緯度地域):約40~50分
太陽の沈む角度が浅いため、薄明が長く続きます。 - 東京(中緯度地域):約30~40分
日本の標準的な薄明時間で、春夏秋冬で適度に変化します。 - 沖縄(低緯度地域):約25~35分
太陽がほぼ垂直に沈むため、暗くなるのが早い傾向があります。
一般的に、高緯度地域ほど薄明が長く、低緯度地域ほど早く暗くなるのが特徴です。これは、太陽が沈む角度が影響しているためです。
赤道近くと高緯度地域の違いとは?
地球の自転軸の傾きと太陽の動きによって、赤道付近と高緯度地域では日没後の暗くなるスピードに違いが生じます。
- 赤道近く(東南アジアや南米)
太陽がほぼ垂直に沈むため、日の入りから30分以内に完全な夜になることが多い。 - 高緯度地域(北欧・カナダ・ロシアなど)
太陽が斜めに沈むため、日の入り後2時間以上も薄明が続くことがある。
特に北欧の夏至付近では、「白夜(びゃくや)」と呼ばれる現象が発生し、夜になっても完全に暗くならない日があります。

このように、季節や地域によって、日の入り後の暗くなるスピードには大きな違いがあるのです。
秋の日は「つるべ落とし」?日没後すぐに暗くなる理由

「秋の日はつるべ落とし」の意味とは?

「秋の日はつるべ落とし」という言葉を聞いたことがありますか?
これは、「秋になると日が沈むのが早く、あっという間に暗くなる」という意味の慣用句です。
「つるべ」とは、井戸で水を汲み上げるための桶のことで、ロープを緩めると一気に落ちる様子を表しています。まさに秋の夕暮れは、太陽が急激に沈み、すぐに夜が訪れるように感じられます。
なぜ秋は他の季節よりも早く暗くなるのか?
秋に日が沈むとすぐに暗くなるのには、科学的な理由があります。主な要因は以下の3つです。
- ① 太陽の沈む角度が急になる
春や夏に比べて、秋は太陽が地平線に向かって急角度で沈むため、薄明の時間が短くなります。結果として、日没後にすぐに暗く感じるのです。 - ② 大気中の水分量が減る
夏は湿度が高く、大気中の水蒸気が光を散乱させて薄明を長引かせます。しかし、秋は乾燥するため、光の散乱が少なくなり、暗くなるのが早いのです。 - ③ 日照時間が短くなる
秋分を過ぎると、昼間の時間が短くなり、日の入りの時間がどんどん早くなります。そのため、仕事や学校が終わる頃にはすでに暗くなっていることが多くなるのです。

特に9月下旬から10月にかけては、日の入りの時間がどんどん早まり、日没後に一気に暗くなる感覚が強まります。
秋の夕暮れを楽しむためのおすすめスポット
秋の夕暮れは、空気が澄んでいて美しい夕焼けが見られる絶好の季節です。日没後すぐに暗くなりますが、その一瞬の光景を楽しむために、おすすめのスポットを紹介します。
- ① 江ノ島(神奈川県)
海に沈む夕日が絶景。秋は空気が澄んでおり、遠く富士山のシルエットも見えることが多いです。 - ② 嵐山(京都府)
渡月橋周辺から見る夕日は、紅葉とのコントラストが美しく、秋ならではの風情が楽しめます。 - ③ 美瑛町(北海道)
丘陵地帯に沈む夕日は、幻想的な風景を作り出します。夏とは違い、秋の澄んだ空気がさらに美しさを引き立てます。
日没後すぐに暗くなる秋ですが、その分、夕焼けが鮮やかに見える季節でもあります。「つるべ落とし」のように急に暗くなる前の、美しい時間を楽しんでみてはいかがでしょうか?
日の入りから暗くなるまでの時間を知る方法

簡単に日の入りと薄明を調べる方法(スマホアプリ&サイト)
日の入り後に暗くなるまでの時間を正確に知るには、専用のスマホアプリやウェブサイトを活用するのがおすすめです。以下のようなツールを使うと、現在地や特定の日付の薄明時間を簡単に確認できます。
- ① そら案内(スマホアプリ)
日本の天気予報や日の出・日の入りの時刻がわかるアプリ。薄明の時間も確認可能。 - ② 国立天文台「こよみの計算」
国立天文台の公式サイトでは、日本全国の詳細な日の入り時刻や薄明の時間が調べられます。 - ③ Time and Date(国際的な日照データサイト)
世界中の都市の日の出・日の入り、薄明時間が確認できる便利なサイト。

これらのツールを使えば、撮影や夜景観察など、暗くなるタイミングを事前に計算することができます。
天気や雲の影響で暗くなる時間は変わる?
実際の日の入り後の暗さは、天候や雲の有無によっても変わります。例えば:
- 晴天の日:大気中の光の散乱があるため、薄明が長めに続く。
- 曇天の日:雲が太陽の光を遮るため、日の入り直後に暗くなる。
- 雨の日:全体的に光が少なく、昼間でも薄暗く感じられることが多い。
特に秋冬は、放射冷却による急激な気温低下で霧が発生しやすいため、薄明の時間が短く感じられることがあります。
撮影や夜景観察に適した時間の調べ方

日の入り後の時間をうまく利用すれば、美しい風景や夜景を楽しむことができます。
以下のタイミングを活用しましょう。
| 時間帯 | 特徴 | おすすめの撮影・観察 |
|---|---|---|
| 日の入り直後(0~10分) | 空が赤く染まり、ドラマチックな雰囲気 | 夕焼けの撮影、シルエット写真 |
| 市民薄明(10~30分) | 空に青とオレンジのグラデーションが残る | 夜景の撮影、街灯が点灯し始める瞬間 |
| 航海薄明(30~60分) | ほぼ暗闇に近く、星が見え始める | 星空の撮影、夜の風景撮影 |
| 天文薄明後(60分以降) | 完全な暗闇になり、星空がはっきり見える | 天体観測、天の川撮影 |
特に夜景撮影では、市民薄明の終わるタイミング(約30分後)がゴールデンタイムと言われています。この時間帯を狙えば、美しい「ブルーアワー」の写真が撮れるでしょう。
また、星の観察をするなら、天文薄明が終わる1時間後以降がベストです。これらの時間帯を活用して、夕方から夜にかけての移り変わりを楽しみましょう。
よくある質問(FAQ)

Q1. 日の入りと日没の違いは何ですか?
「日の入り」と「日没」は基本的に同じ意味として使われることが多いですが、厳密には日の入りは太陽の上端が地平線に沈む瞬間を指します。一方、「日没」という言葉はもう少し広義で、夕焼けが消えるまでの時間を含むこともあります。
Q2. 日の入り後にすぐ暗くならないのはなぜ?
日の入り後すぐに暗くならないのは、大気が太陽の光を散乱させるためです。この光の散乱によって、薄明(トワイライト)の時間が生じ、日没後もしばらく空が明るく保たれます。特に春・夏はこの時間が長く、秋・冬は短くなります。
Q3. 高緯度地域ではなぜ薄明が長いのですか?
高緯度地域では、太陽が地平線に対して斜めに沈むため、薄明の時間が長くなります。例えば、フィンランドやカナダなどでは、夏には夜になっても完全に暗くならない「白夜」が発生することもあります。
Q4. 日の入りの時間を正確に知る方法は?
日の入りの時間は、スマホアプリやウェブサイトで簡単に調べることができます。特におすすめのツールは以下の3つです:
- 国立天文台「こよみの計算」
- Time and Date(世界の日照時間を調べるサイト)
- そら案内(天気予報・日の入り情報を確認できるアプリ)
Q5. 薄明の時間は季節によってどれくらい変わる?
薄明の時間は、季節によって大きく異なります。一般的な目安は以下の通りです:
| 季節 | 薄明の時間 | 特徴 |
|---|---|---|
| 春 | 約30~40分 | 徐々に日が長くなり、薄明の時間も延びる |
| 夏 | 約40~60分 | 最も長く、暗くなるまでに時間がかかる |
| 秋 | 約25~35分 | 「秋の日はつるべ落とし」と言われるほど急激に暗くなる |
| 冬 | 約30~45分 | 日没の時間が早く、暗くなるのも早い |
特に夏は薄明の時間が長く、冬は短いのが特徴です。旅行や撮影計画を立てる際は、この違いを考慮すると良いでしょう。
まとめ
日の入りから暗くなるまでの時間は、季節や地域、天候によって大きく異なります。特に「秋の日はつるべ落とし」と言われるように、秋は他の季節に比べて急激に暗くなるのが特徴です。一方、夏は薄明が長く続き、日の入り後もしばらく明るさが残ります。
また、薄明(トワイライト)には「市民薄明」「航海薄明」「天文薄明」の3つの段階があり、それぞれ異なる明るさがあります。この知識を活用すれば、夜景や星空観察、撮影のタイミングをうまく調整することも可能です。
日の入りや薄明の時間は、国立天文台のサイトや専用アプリを使えば簡単に確認できます。旅行やアウトドア、撮影の計画を立てる際には、ぜひ活用してみてください。

この記事を参考に、日の入りから暗くなるまでの変化をより深く理解し、美しい夕暮れの時間を楽しんでください。